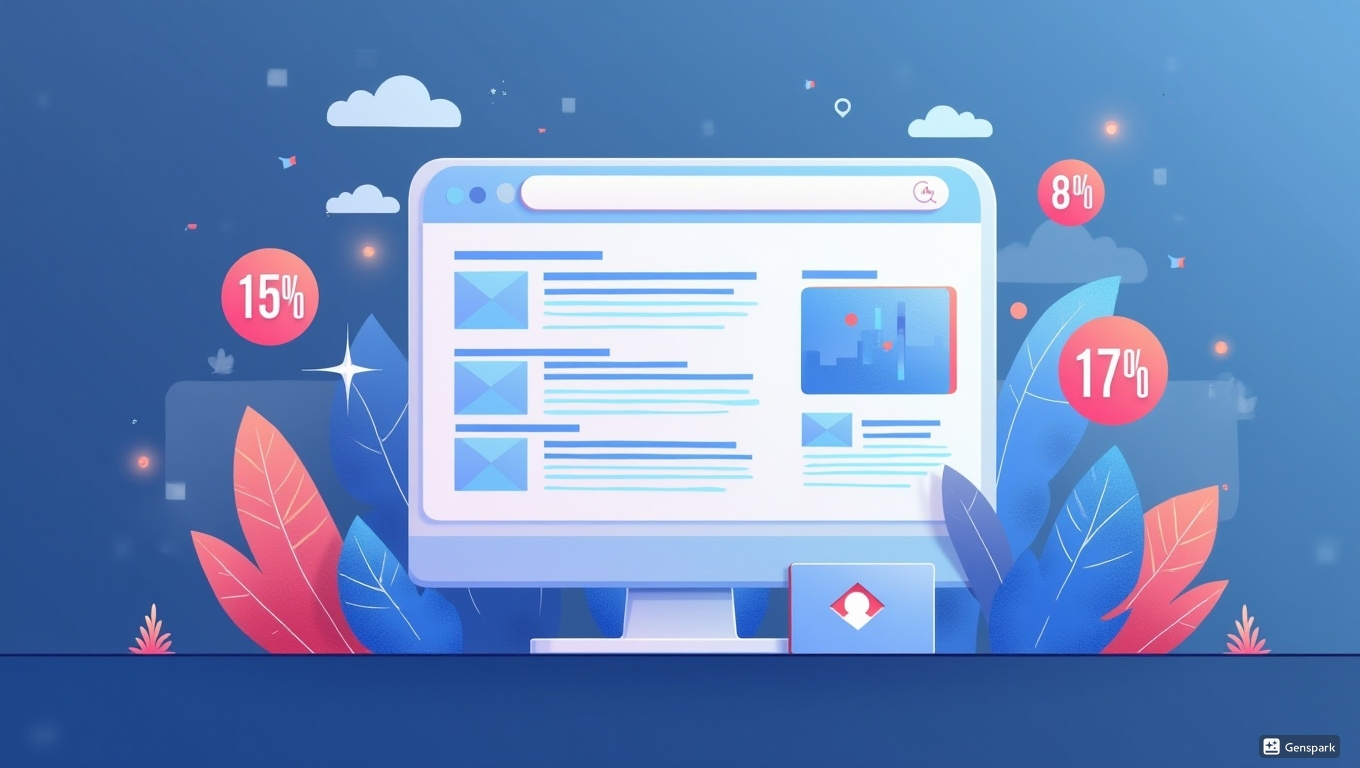非営利団体Pew Research Centerが2025年7月22日に発表した調査によると、GoogleのAI Overviews機能が検索結果に表示される場合、ユーザーがウェブサイトのリンクをクリックする確率が大幅に低下することが明らかになった。
調査は米国成人900人のウェブブラウジング活動データに基づいて実施された。
2025年3月の分析では、調査参加者の58パーセントがAI Overviewsが表示される検索を少なくとも1回実施した。AI要約が表示された場合、ユーザーは全訪問の8パーセントで従来の検索結果リンクをクリックしたが、AI要約が表示されなかった場合は15パーセントでクリックしており、約2倍の差が生じている。
AI Overviews内のソースリンクについては、わずか1パーセントのユーザーしかクリックしなかった。AI Overviewsが表示される検索は全体の18パーセント(約5回に1回)の割合で発生し、この場合ユーザーがブラウジングセッションを終了する確率は26パーセントとなり、従来の検索結果のみの場合の16パーセントより高くなった。
10語以上の長い検索クエリではAI Overviewsが53パーセントの確率で表示されるが、1-2語の短い検索では8パーセントに留まる。最も頻繁に引用されるソースはWikipedia、YouTube、Redditで、AI要約全体の15パーセントを占めている。
From:
Google AI Overviews are killing the web, Pew study shows (again)
【編集部解説】
ウェブエコシステムの根本的変化を示すシグナル
今回のPew Research Centerの調査結果は、単なる検索行動の変化を示すものではありません。AI Overviewsがもたらしているのは、過去20年以上にわたって続いてきた「検索→クリック→サイト訪問」という基本的なウェブエコシステムの根本的な変化です。
この変化の本質は、情報の流通構造そのものが変わりつつあることにあります。従来、ユーザーは複数のウェブサイトを訪問して情報を収集し、比較検討を行っていました。しかし、AI Overviewsは複数のソースから情報を統合し、検索結果画面上で直接回答を提供することで、この従来のプロセスを短縮しています。
「ゼロクリック検索」現象の加速とその意味
調査データが示す最も重要な変化は、いわゆる「ゼロクリック検索」の加速です。AI Overviewsが表示される場合のセッション終了率が26%に達し、従来の16%から大幅に上昇している点は特に注目に値します。
この現象は、ユーザーが求める情報の質と深さによって大きく左右されます。基本的な事実確認や簡単な質問については、AI Overviewsで十分な回答が得られるため、追加のクリックが不要になるケースが増えています。実際に、10語以上の詳細な質問形式の検索では53%の確率でAI Overviewsが表示される一方、1-2語の短い検索では8%に留まることからも、複雑なクエリほどAI要約の対象となりやすいことが分かります。
業界別影響の格差と新たなビジネス機会
興味深いことに、AI Overviewsの影響は業界によって大きく異なると推測されます。調査結果から、Wikipedia、YouTube、Reddit、政府サイト(.gov)が頻繁に引用されていることが明らかになっており、これらの特徴を分析すると一定の傾向が見えてきます。
政府サイトはAI Overviewsで従来の検索結果の3倍(6% vs 2%)引用されており、信頼性の高い公的情報源への偏向が見られます。一方で、YouTubeが引用される場合は動画コンテンツという特性上、実際のサイト訪問につながりやすい可能性があります。
この傾向から考えると、「正解が明確な情報」を提供するサイトほど大きな影響を受ける可能性があります。逆に、独自の視点や体験に基づくコンテンツ、専門的な分析や解説を提供するサイトでは、影響が限定的である場合も多いと予想されます。
テクノロジー企業とパブリッシャーの新たな関係性
この変化の背景には、テクノロジー企業とコンテンツパブリッシャーの間の力関係の変化があります。従来の検索エンジンは「交通整理」の役割を果たし、ユーザーを適切なサイトに誘導していました。しかし、AI Overviewsは「情報の統合と再構成」を行うため、オリジナルコンテンツの価値チェーンに直接介入する形となっています。
GoogleはこのPew調査の手法に異議を唱えており、「欠陥のある手法と偏ったクエリセットを使用している」と反論しています。同社は「AI機能により人々はより多くの質問をすることができ、ウェブサイトとつながる新しい機会を創出している」と主張し、「日々数十億のクリックをウェブサイトに誘導しており、総合的なウェブトラフィックの大幅な低下は観察していない」と述べています。
規制環境と業界への長期的影響
米国では既にGoogleの検索事業が独占禁止法違反と判決され、オンライン広告事業についても同様の判断が下されています。このような規制環境の変化と、今回のPew調査が示すAI Overviewsの影響は、ウェブエコシステム全体の再構築を促す可能性があります。
出版業界は既に深刻な状況に直面しており、2025年は「ジャーナリズムにとって厳しい年」となっています。CNN、Vox Media、HuffPost、LA Times、NBCなどで相次いで人員削減が実施され、過去3年間で約1万人のジャーナリストが職を失っています。
ポジティブな側面と新たな可能性
一方で、AI Overviewsには明確なポジティブな側面も存在します。ユーザーの情報アクセス効率は大幅に向上し、複雑な質問に対して包括的な回答を得られるようになりました。また、情報の信頼性向上も期待されており、複数のソースから情報を統合することで、より客観的な視点を提供できる可能性があります。
Googleが主張するように、AI機能により「人々がより多くの質問をする」ようになれば、新たな検索需要の創出につながる可能性もあります。さらに、AI Overviewsで引用されることは、サイトの権威性や信頼性の証明にもなりえます。
長期的視点での技術進化と社会への影響
より長期的な視点では、AI Overviewsは検索という行為そのものの定義を変える可能性があります。現在のAI Overviewsはまだ初期段階にあり、より高度な推論能力と対話性を持つ次世代システムの開発が進んでいます。
この変化は、情報リテラシーの重要性をさらに高めることになるでしょう。ユーザーは、AIが提供する情報の質や信頼性を適切に判断する能力がより求められるようになります。同時に、コンテンツ制作者には、AIでは生成できない独自の価値を創出することがより重要になってきます。
今後の展望と課題
現在の状況は、インターネットの商業化初期に似た過渡期の状況と言えるかもしれません。新しいテクノロジーが既存のビジネスモデルに挑戦し、業界全体が新たな均衡点を模索している段階です。
重要なのは、この変化を単なる「脅威」として捉えるのではなく、新たな機会として活用する視点を持つことです。AI時代に適応したコンテンツ戦略の構築、新しい収益モデルの探索、そしてユーザーにとって真に価値のある独自コンテンツの創出が、今後の成功の鍵となるでしょう。
【用語解説】
AI Overviews
Googleが2024年から提供している検索機能で、生成AI「Gemini」がユーザーの検索クエリに対してウェブ上の複数の情報源から要約を作成し、検索結果の最上部に表示する。従来の「SGE(Search Generative Experience)」から改名された。
ゼロクリック検索
ユーザーが検索結果ページで必要な情報を得られるため、個別のウェブサイトをクリックせずに検索を終了する現象。AI Overviewsの普及により加速している。
セッション終了率
検索結果ページを訪問した後、そのままブラウジングを終了する割合。AI Overviewsが表示される場合は26%、表示されない場合は16%となっている。
【参考リンク】
Pew Research Center(外部)
今回の調査を実施した米国の非営利調査機関。世論や社会問題に関するデータを提供。
Google(外部)
AI Overviews機能を開発・提供する世界最大の検索エンジン運営企業。
The Register(外部)
英国のテクノロジーニュースサイト。本件の元記事を報じたメディアの一つ。
【参考記事】
Pew Research Center公式報告(外部)
今回の調査の原典資料。AI要約表示時のクリック率低下など詳細なデータを公開。
Ars Technicaによる分析記事(外部)
Pew調査を技術的観点から分析し、SEOやパブリッシャーへの影響を解説。
CNETによる解説記事(外部)
調査詳細と出版業界が直面する構造的問題、ジャーナリズムの現状について解説。
MediaPostによる業界分析記事(外部)
広告業界の視点からPew調査を分析し、パブリッシャーの収益モデルへの影響を検討。
【編集部後記】
AI Overviewsの影響は、私たち情報を扱う人間にとって避けて通れない現実となりました。皆さんの業界や関心分野では、すでにこうした変化を感じていらっしゃるでしょうか?
特に気になるのは、コンテンツ制作者や中小企業の皆さんがどのような対策を検討されているかです。従来のSEO戦略の見直しはもちろん、AI時代に求められる「独自価値」とは何か、一緒に考えていきませんか?